連載「つつむ」をつくる 第3話
「つつむ」をつくる
1976年に、私たちの会社は「パッケージアート」という名称に変わりました。
先代の「つつむ技術だけでなく、そこに豊かさを感じさせるものがなければならない」という信念を表したものです。「アート」には”技術”と”表現”との意味を込め、パッケージを通じて広がる豊かさを意識しています。
私たちのモットーである「つつむ」をつくるという言葉には、そうした思いが込められています。豊かさの源泉は、お客様の製品でありサービスです。その価値はお客様のブランドにあります。「つつむ」をつくるとは、お客様のブランドをパッケージを通じて支えるということです。私たちは、お客様のブランディングのパートナーとなりたいと考えています。
この思いをお伝えしたく、4話のブログに綴りました。今回は、その第3回目です。
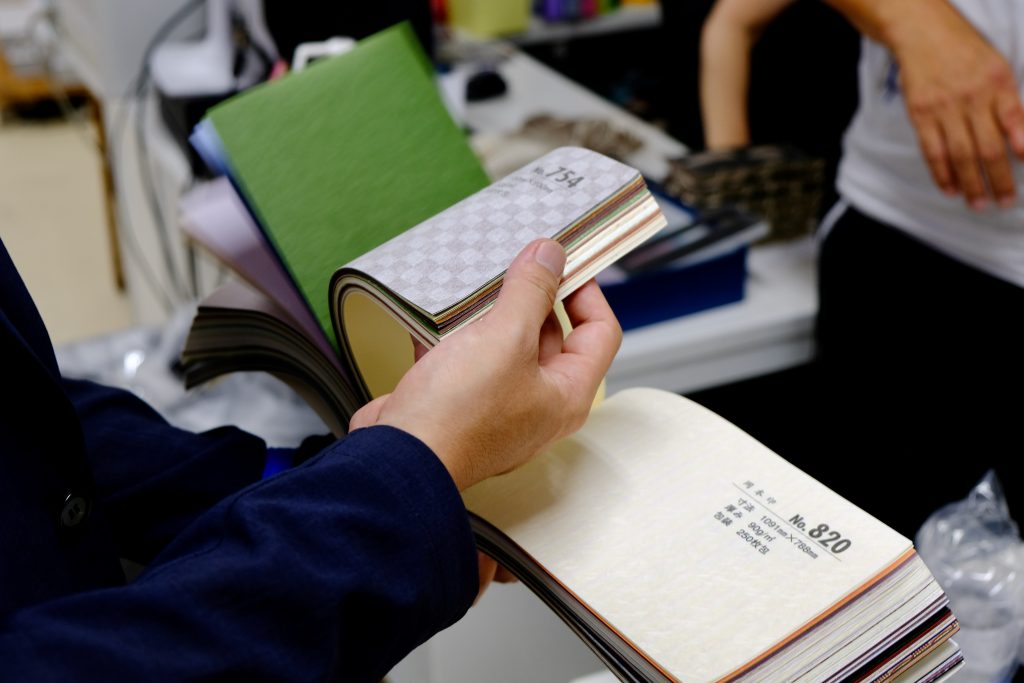
第3話:パッケージは、カスタマージャーニー
パッケージは、おしゃべり好き
街を歩いていると、パッケージは「おしゃべり好きだな」と感じる時があります。あちこちから、いろいろな声で話しかけてくれる。本当に賑やかです。
季節の移り変わりや、様々なイベントや行事に合わせて、声のトーンを変え、多彩な音階を奏で、歌でも歌うように話しかけてくれます。街中はいつも盛大なコーラスが鳴り響いているようです。
パッケージには、伝える力があると私達は信じています。実際に「声」があるのです。その「声」に耳を傾けてみてください。
ある人にはかすかに、ある人には大きく聞こえます。それは呼びかけであったり、ささやきであったり、朗読であったり、演説であったり、多種多様で個性豊かです。遠慮がちな「声」もあれば、堂々とした太い声もあります。
世界はパッケージの「声」にあふれているのです。

「つつむ」とは、カスタマージャーニーの演出
その「声」に深く耳を傾けるとき、私たちは「つつむ」ことの意味をもっと深く知ることにもなります。「つつむ」とは、どういうことなのでしょう。パッケージの声を聞いてみましょう。
「開けて欲しい」
そんな声が聞こえてきませんか。
「つつむ」ことは、本質的に「開ける」瞬間を待つプロセスなのです。「つつむ」ことの意味は「開封」されてはじめて完成します。永遠に開けられることのないパッケージは、永遠にパッケージとして完成しえない。開けられてこそ、パッケージは「つつむ」意味を全うします。
空けた時の微かな空気の変化。朱塗りのお椀の蓋を開ける時の、あのなんとも言えない高揚感にも似た幸せを贈りたくて、人はパッケージを選びます。
「つつむ」とは、製品や作品を箱に閉じ込める行為ではありません。
「つつむ」をつくるとは、お客様の製品や作品を手にしたユーザーが、パッケージを手にして封を開ける瞬間までの一連のプロセス、つまりカスタマージャーニーを演出する仕事なのです。私たちは、その演出のプロフェッショナルになりたいと思っています。

共有/シェア

量産単価の目安が分かる「パッケージ製作事例集 – バックヤード資材編」を公開
バックヤード用のパッケージ・梱包資材は、日常業務で無理なく使えることが重要です。一方で、「どこまで作り込むべきか」「量産時のコスト感」は判断が難しいポイントでもあります。 本資料では、当社の製作事例をもとに、バックヤード

パッケージは完成!さて、どうやって発送する?
梱包資材の基本構成と考え方 商品とパッケージが完成し、いよいよ出荷――。その段階で見落とされがちなのが「発送用資材の設計」です。 実際の出荷直前になってから「この梱包で本当に安全?」「外箱や緩衝材は何を基準に選ぶべきか」

量産時の費用目安が分かる「パッケージ製作事例集 – 壊れ物編」を公開
ガラス製品や精密機器など、特段配慮が求められる「壊れ物」のパッケージ製作。設計の正解が見えにくい中で「この仕様を量産したら、どの程度の費用感になるのか」は多くの方が気にされるポイントです。 そんな疑問に応えるべく、壊れ物

特注サイズの梱包箱が高くて断念… そんな時の救世主“ダンボール板”という選択肢
「本などの厚みが無いものを1つ送りたいだけなのに、手元に大きい箱しかない」配送物に対してちょうど良い大きさの箱を探すというのは梱包時の永遠のテーマであり、なかなか悩ましいところです。そんな悩みを今回ご紹介する「たとう式」梱包方法をご紹介します。





